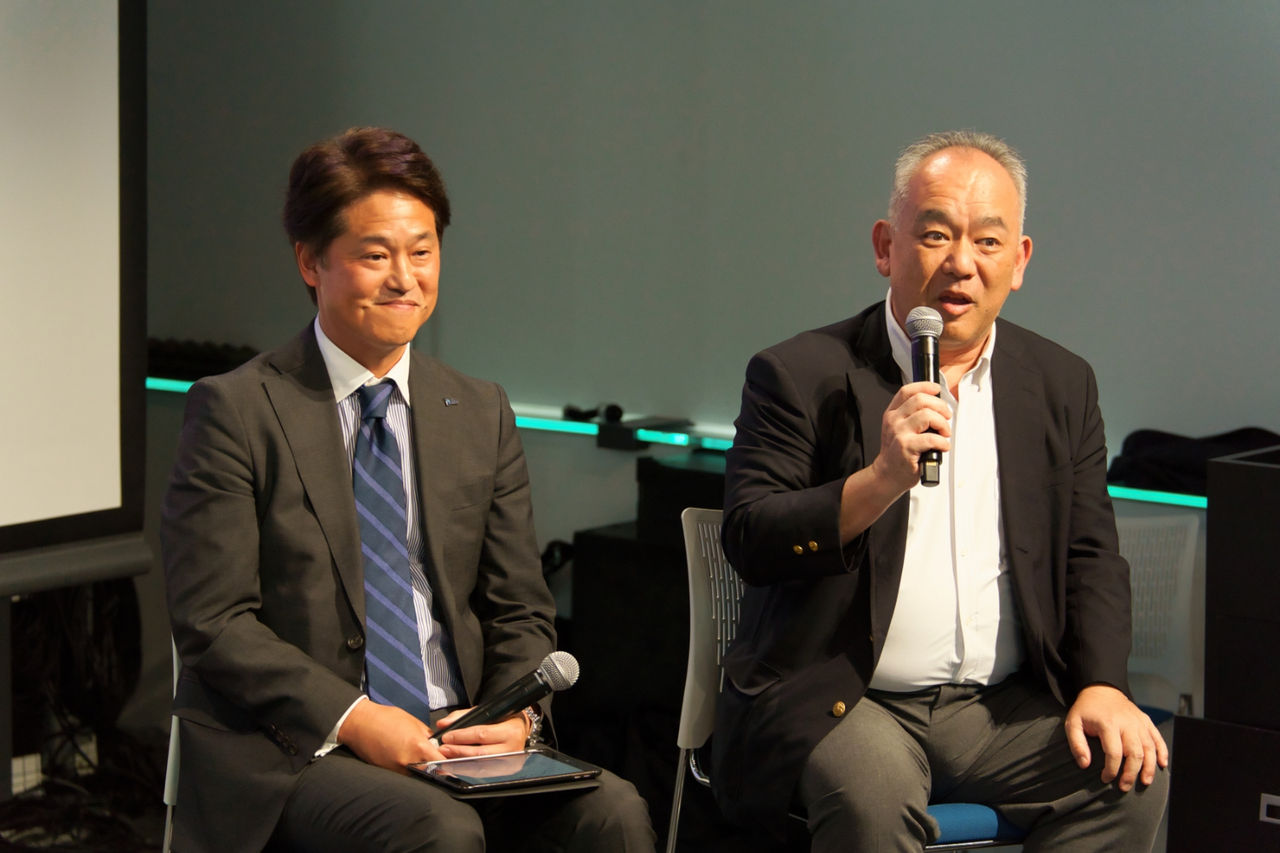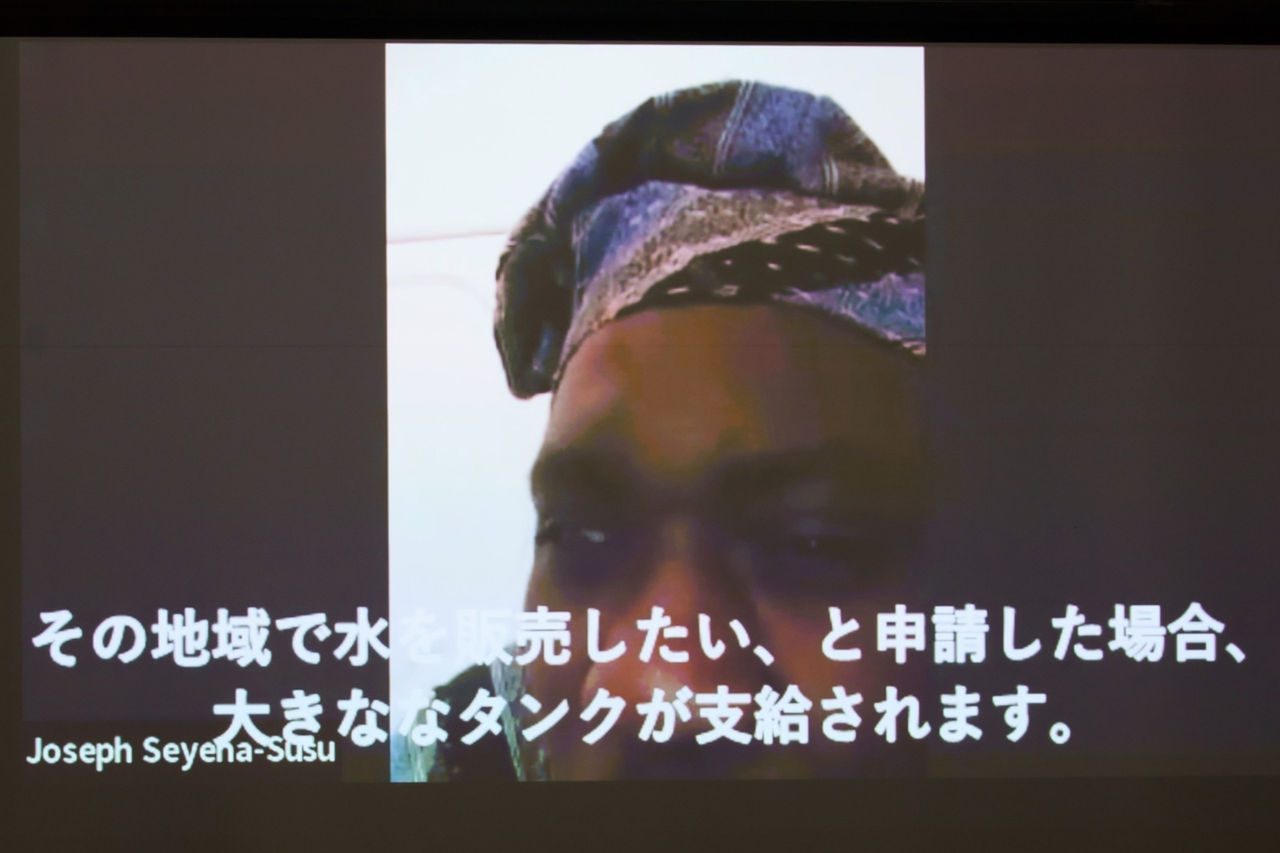スクリーンリーダー(読み上げ機能)の進歩やスマートフォンの普及などによって、視覚障がい者は外出時のナビゲーション、金融サービスや決済、写真撮影・管理、文字認識など多様な方面でテクノロジーの助けを借りることができるようになりました。自らできることが増えた一方で、周囲からのサポートを求めにくい雰囲気にもなっていると中根さんは指摘します。また川本さんはAR・VRといった視覚優位の技術が発展する中で、視覚障がい者が置いていかれる場面も生まれているといいます。
そして三者が口を揃えて訴えたのが、セキュリティ強化の取り組みが視覚障がい者に与える困難についてです。画像を認識したり、パスワードをなぞったりする形式による本人確認は視覚障がい者にとっては非常に困難で、自分の資産にすら自由にアクセスできないという状況が起こっています。